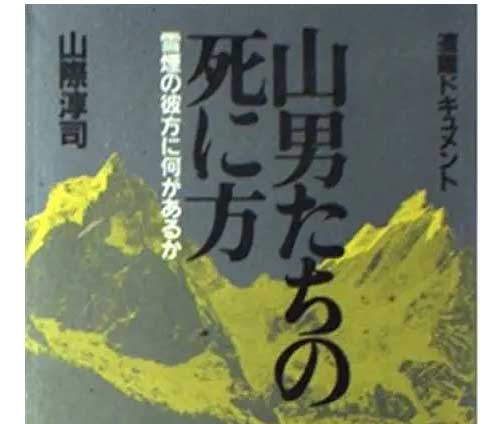加藤保男というクライマーを、私が知ったのは、週刊誌の記事から。その記事とは、こんな内容だった。
「1973年10月26日、加藤はエベレストの頂上に立った。しかし下山途中にボンベが切れて酸欠になり、高度8650mの氷雪上にビバーク (「8600mのところに、目に見えない空気の壁がある」と加藤は言う)
凍傷にかかった加藤の13本の指は黒い木炭のようにぶら下がり白い骨がのぞいた。手術では全身麻酔を拒否して局所麻酔を望み、ヤスリでギシギシと落とされる13本の自分の指を見つめて叫んだ。『エベレストの野郎』と」
何とも、壮絶。
1949年、埼玉県大宮市(現、さいたま市)に生まれた加藤は、日本大学文理学部体育学科を卒業後、アイガー、グランド・ジョラス、マッターホルンのアルプス三大北壁登攀を達成する。
1973年、ネパール側東南稜から、エベレスト登頂に成功。ポストモンスーン期(秋季)における世界初登頂という栄冠と引き換えに、前述のごとく、足指すべてと右手指3本を失った。
しかし屈することなく、1980年、今度はチベット側の北東稜からエベレストに登頂、ネパール・チベット両側から登頂した世界初のクライマーとなる。
さらに1982年12月27日、冬期エベレスト登頂を果たし、世界初の3シーズン(春・秋・冬)登頂者となるものの、下山中に消息を絶ってしまう。
なお、1有余年後の1984年2月13日には、マッキンリーで、植村直己が消息不明となっている。
何が、加藤や植村たちアルピニストを、マイナス50度、ジェットストリームが吹き荒れる8000mの氷壁に挑ませるのか?
誰もが思うそんな疑問を、解きほぐそうと試みたのが「スローカーブを、もう一球」などで知られる、スポーツノンフィクション作家の山際淳司。
山際が著した「山男たちの死に方」、その書き出しは、「加藤保男は、竜舌蘭の花を見たか」と始まる。
エベレストに憑りつかれた男・加藤は、30年に1度しか花をつけないとも言われる、ヒマラヤの竜舌蘭に出会っただろうか、との、山際の思いを馳せた書き出しだ。
第1章 雪煙の彼方に何があるか
。
加藤は生前、「雪煙をめざして」という著書を1冊遺している。
この読後感について山際は、「本を書くという行為は、彼がなし遂げたことの排泄物なのかもしれない。実際はもっとドラマチックであったはずであるのに、言葉は存外そっけない。彼が書き連ねた言葉に生気はない」と手厳しい。
と同時に「それは逆に、加藤保男が行動者として本物であることを証明している。行為そのものに興味を持つ人間にとって、あとからそれをふりかえることなど、どうでもいいことなのだ」と分析したうえで、「ハッとする文章もあった」とも述べている。。
その文章とは
- 戦争体験者はよく音で、着弾距離や弾の大きさを判断できるというが、ぼくらもシュルシュルとかキーンという音で、それがどういう落石か、ある程度判断できる ようになっていた。
- そこには、すさまじいまでの夕焼が広がっていた。空気も雲も一体となって燃え、黄金色からばら色へ、さらに杏色へと柔らかな階調を織りなしていた。そして左の方遠くに、マッターホルンが望まれた。ぼくはユマールにぶら下がったまま、息をころして眺めた。谷間には夜が訪れているが、ウォーカー稜の側壁はライラック色に映え、次第に鉄色に向かって変化してゆき、そして突然闇の中に姿を没した。
「加藤が街でではなく山で体験したこと、見たものを、この二つの文章が象徴している。彼は山に行けば戦士のごとく、また、信じられな いほどの美しさを誇示する自然を前にして一人の詩人になってしまうわけである。その一瞬の、生のきらめき。それを心の深いところで受けとめてしまった人間は、 いつまでもそれを追い求める。危険を顧みず、果敢にアタックする。
功名心がなければ先に進めない。しかし、功名心だけでは自分の命を取引の材料にはできない。加藤をはじめとした尖鋭的アルピニストには、心の深いところに別の衝動があるのだ。危険の向こう側にこそ一瞬の生のきらめきがあるのではないかと、彼らを突き動かすものがある。
彼らはもちろん、死のうと思って山に行くわけではない。あらゆるケースを想定し、それを乗りこえられる体力、知力、技術があると信ずるから出かけていくのだ。しかし、それでも死とすれすれの関係になることを知っている。
アルピニズムとは、山においてより多くの困難を自ら引き受け、それを乗りこえていくという姿勢を意味している。尖鋭的アルピニストであればあるほど、生と死のきわどいつり橋をわたることになる。死を意識せずにはいられない。死はいつも、彼らのすぐ隣にいるのだ。それを承知で、一部のアルピニストたちは雪煙を求めて氷壁にたち向かっていく。
彼らは、いわば死に対する確信犯である。彼らに対しても、死は突然にやってくるが、しかしそれは偶然ではない。なかば必然的にやってくる死である。
尖鋭的アルピニストたちはそれを知っている。知りつつなお、死の領域に足を踏み入れてしまうのだ。生と死が紙一重で交差している領域が、彼らにとっては限りなく魅力的であるからだろう」
翻って山際は、街での日常生活に言及する。
「人が自然を相手にする際に直面しなくてはならない危険が、テクノロジーによっ てあまりにも最小限に押えられてしまっている。
そこから生まれる倦怠感。これはやっかいなものだ。それらはぼくらの日常生活に、鎖のようにからみついて、ついてまわる。そいつを気まぐれにではなく、心底ふりきろうと思えば、異空間に向かってダッシュするほかない。闇のなかを突っ走れるだけの決意がなければだめだ。危険を自分のなかに引き受けることによって、初めて倦怠感は消失する」
アルピニストと現代人との対比、それが山際にとって、本書執筆の原動力となっている。
「加藤は、危険を引き受けてなお、先に進もうとした。冒険主義だって? いいではないか。すさまじい勢いで雪煙のかなたに突っこんでいった男たちは、もはや何も語りはしない。が、向こう側の世界からメッセージを送ってきている。
何人かの男たちの”死”は、残された者に生き方を示唆する。皮肉なことだが、そういう側面がある。耳を傾けてみるべきだ。あらゆる危険から守られて途方に暮れている現代人に、長らく忘れていたもう一つの世界からのメッセージが聞こえて くるはずなのだ」
第2章 ザイルのトップは譲れない
加藤保男と同時期に活動したクライマーに、1937年、現在の東京都荒川区に生まれた森田 勝という男がいる。華々しい記録を打ち立てた加藤とは異なり、ビッグタイトルには縁遠かった。第2章で山際は、この「不運の男」にスポットを当てる。
「古い新聞のスクラップをめくっていくと、何か所かで森田に関する記事と出会うことができる。たとえば、1973年の秋、エベレストに向かった「日本エベレスト南西壁登山隊」、これは日本の山岳界をリードしてきた第二次RCC (ロック・クライミング・クラブ) のエベレスト隊のことだ。
そのメンバーのなかに、森田勝の名前を見つけることができる。加藤保男も、含まれている。加藤がエベレストの東南稜から頂上をめざし、酸素が切れたなかでビバーク、手足の指を凍傷で失ったのが、このときである。
この登山隊の主目標は、隊の名前にもついているとおり、南西壁にあった。加藤が登った東南稜は二次的なアタックだった。
森田は南西壁をアタックするメンバーとして認められていた。ということは、森田がこのパーティーの中心隊員の一人であったことを意味している。
現地に着くと、いくつかのアクシデントに見舞われた。シェルパが一人、雪崩に巻きこまれてしまった。それによってシェルパの士気がいちじるしく低下した。
季節が秋であったことも影響している。冬が近いのだ。エベレストが日一日と魔の山に変わっていくことを、シェルパたちは知っている。
そういうなかで仲間が一人、雪崩にやられた。残されたシェルパたちが逃げ腰にな ったとしても不思議ではない。
天候もよくなかった。キャンプを築き、アタックの準備が整っても天気はいっこうに回復しない。しかも南西壁は過去、何人ものアルピニストが挑み、いずれも敗退したといういわくつきの難所である。
南西壁攻略は不可能なのではないか、という空気が広がり始めた。が、隊として「戦果」は何が何でも残さなければならない。
そこでクローズアップされてきたのが東南稜ルートだった。このルートは過去、何人ものクライマーによって登られている、エベレストのオフィシャル・ルートで ある。こちらに主力を傾ければ、とりあえず「エベレスト秋期初登頂」という実績だけは残せる。
加藤保男はこの東南稜のアタック隊として選ばれた。
森田は無理かもしれないと思いつつも、南西壁をアタックする側に残った。
南西壁アタックは、案の定、失敗した。
世界で初めて秋期のエベレストの頂上に立った男として、加藤保男・石黒久の二人の名前が残った。
森田の名前は残らなかった。森田がそのエネルギーを東南稜に向ければ事態は変わっていたはずだ。器用な人間であれば、そうしただろう。
どんな方法を使ったって、勝てばいいのさ。結果がすべてだからね。そういう考え方がある。正論にちがいない。人は結果しか見てくれないのだから。
しかし、それによって失われるものもある。自分に対するプライドである。
森田はそれを失いたくなかった。人のために山に登っているのではない。自分のために登っているのだ。
初志を曲げてしまったらどんなに素晴らしい結果が得られ ても、ちっともうれしくはない。
森田勝は、自分のプライドにこだわった。そして栄光に逃げられた。そういう男だ。どうして彼を敗者といえるだろう」
エベレスト遠征から4年後、1977年8月、40歳の森田はヒマラヤの西、カラコルム山脈のK2をめざしていた。日本山岳協会が主催するK2登山隊のメンバーに選ばれたのだ。
しかし、登頂メンバー発表の結果、森田は第2次アタック隊にまわされる。あくまでも一番にこだわる彼は思い悩む。
「彼はあまりにも熱い情熱を心にかかえてしまっている。自分でそれを冷やすことができない。その苦しみから逃れるために黙々と、誰よりも重い荷を背負い、山を歩いた。苦業を課した。それでも、だめだった。
自分に正直に生きるしかない。彼はそう決めた。第5キャンプからベース・キャ ンプをトランシーバーで呼び出した。
『今から下ります』
そういってしまった。
待ってくれとベース・キャンプはいった。チームワークを乱さないでくれ、と。
アタックは目前に迫っているのだ。しかし、森田はガンとして受けつけない。交信を切ると、一人、ベース・キャンプに向けて下りはじめた」
ところが、皮肉な結果が待っていた。第一次アタックは失敗、日本人として初めてK2に立ったのは、森田を除く第二次アタック隊のクライマーたちだった。
「それみたことか、ということはできる。が、それは結果論だ。森田は何もいわなかった。彼は、自分のやり方をとおした。結果からいえば哀しくもこっけいだが、彼は自分を守ったのだ。
今どき、森田のような男ははやらないだろう。彼の生き方は、じつに不器用だ。
社会とうまく折り合うことができない。人間関係を円滑に運ぶことも得意ではない。
しかし、この男がわき目もふらず直進すると、そのパワーはすさまじい。ナイフの鋭さはない。切れ味もよくはない。が、斧で大木を倒すような力がある。底知れぬエネルギーを秘めている」
森田はエベレストから帰還後に結婚し、子どもも生まれた。スポーツ用具メーカーの技術顧問という仕事も安定してきた。K2へ行ったとき、それが山における最後のチャンスだろうと彼はいっている。年齢のことも考えなければならない。いつまでも旅人でいることはできない。
「生活のペースが一定してきた。毎日が同じような時間の流れで過ぎていく。それが日常というものだ。その流れに身をまかせてしまえば、いいのだ。
森田は、自分を強いるようにして日常に身を置いた。しかし、そうすればするほど心のなかにポッカリと大きな空洞ができてしまうのだった。
そこに風が吹きこんでくる。
ある日、その風が嵐のように吹き荒れてしまった。長谷川恒男がマッターホルンに次いで、冬のアイガー北壁も単独で登ったというニュースに接したのだ。
これにより長谷川は、世界初のアルプス三大北壁冬季単独登頂を達成するためにグランド・ジョラスを残すのみとなった。
長谷川より先にグランド・ジョラスに登りたい、それはとめようのない衝動だった。もう一度、日常から脱してみたい」
森田は冬季単独登頂をねらい、ヨーロッパへ向かう。
1979年2月18日、北壁(ウォーカー側稜)にアタックするが、休憩中にフックが外れて50メートル落下、4時間後に意識を取り戻したときは、すでに夕刻になっていた。しかも左足骨折・胸部打撲・左腕も動かない状態。宙づりのまま、幻覚と戦いながら夜を明かし、翌日、右手・右足と歯で25メートルの決死の登攀を行い、6時間以上かけて荷物のあったテラスに戻った。
そこでまた夜を明かし、翌日にフランス陸軍の山岳警備隊に救助されることになる。
「長谷川恒男の成功を、森田はシャモニーの病院のベッドの上で知った。人は、いつか自分の終焉を知るときがある。森田は、もはや自分の時代でないことにいやでも気づかされることになった」
しかし物語にはもう少し、先がある。
「翌年、森田は再びグランド・ジョラスへやってきた。骨折した足には、骨と骨をつなぐビスが入っていた。
それでも大丈夫だと、彼はいった。
パートナーとして若い二十代の日本人アルピニストがいた。今度は一人ではない。
グランド・ ジョラスを、ザイルのトップをおれが握って登りきってみせるといった。
1980年2月19日、森田のパーティーは登攀を開始した。順調だった。そして24日がやってくる。頂上まであと400m地点まで到達した。
遭難の瞬間を見た人はいない。
翌25日、森田の死体が発見された。
約800m、落下したとみられている。二人とも即死だった。
最後まで、森田勝はザイルのトップを譲らなかった。決して器用ではなかった。
しかし、己れを燃焼させるということに関していえば、彼ほど激しく燃えたクライマーは少ない。
付き合いにくい奴だと、森田は周囲の人間にいわれたはずである。わがままだ、と冷ややかにいわれたことが何度もあっただろう。
どういわれても、彼はあくまで彼でありつづけた。自分に対する批判に耳を傾けはしたが、自分の生き方に迷いはしなかった。まっすぐに突き進んだ。絵に描いたような栄光はないにしても、十分、山で燃えることはできた。
それでも、まだ不足なのだ。
満たされないものがあり、心にすきま風が吹いてしまう。危険を承知で、もう一度、もう一度と、夢を追ってしまう。
そんな夢、絶対にかなえられるはずがないんだと、現実主義者はいうだろう。いい加減に目をさまさないと、とんでもないことになってしまうぞ、と。
にもかかわらず、男というものは時として、夢にこだわり、夢を見つづけるのだ。
いい話がある。
ザイルを組んでいるパートナーがもし転落したらどうするか、ということが話題になったとき、森田は『おれなら見棄てていくよ。ザイルは切ってしまう。おれ一 人になっても、とにかく山を征服するんだ。そのためにおれはいつもナイフを持ってる。ザイルを切るためさ』と言ったという。若いころの話だ。
その後、何年かたって、森田の目の前でパートナーが転落してしまった。アイガーに登っているときだ。
彼が本物のエゴイストだったら、若いころいってたように『ザイルを切った』だろう。しかし、森田には、それができな かった。登攀を中止して、ヘリコプターの出動を要請した。
自分のことに関しては、彼は頑固なまでに我をとおした。それによってこうむるマイナスも自分で引き受けた。他人に甘えることはなかった。そういう男が持っている他人に対するやさしさが、このときの話から伝わってくる。永遠のロマンチストが持っている、やさしさである。
そして森田は、何も残さずに黙って死んでいった」
なお、森田の滑落死について wikipedia にこんな記載がある。「森田の遺体発見者は、森田のパートナーが先に滑落していると思しき場面を目撃しており、森田は二人を繋ぐザイルを切ることなく、パートナーを助けようと苦闘した結果ともに転落したのではないかと推察している」
第3章 一人だけの北壁を登る
1973年の第2次RCCによるエベレスト遠征で、ビバーク中の加藤を救助したのが、サポート隊として参加した長谷川恒男だ。のちの1979年3月4日 、世界初のアルプス三大北壁冬期単独登攀を成功させる男だ。
「醒めたソロ・クライマー」と山際が表現する長谷川の、その哲学に第3章では迫る。
第2次RCCによるエベレスト遠征時に長谷川は、エベレストのピークを目前にした加藤の手相を見て、生命線の傷を指摘したというエピソードがある。
これを山際は、「長谷川が、逸る加藤の気持ちを静めさせようとしたのではないか」と分析する。
「長谷川には冷静な一面がある。単にエモーショナルなだけではない。どこか、醒めているのだ。それは一人で考 え、一人で行動するタイプの人間に共通しているポイントである。エベレストには パーティーを組んで来ているが、その後、長谷川はソロ・クライマーになる。一人で、氷壁に挑戦しようとするのだ。
ソロ・クライマーは状況を自分で判断し、自分で決断を下さなければならない。単にエモーショナルなだけの人間は、往々にして判断を誤る。パッショネイトな自分を見つめているもう一人の冷静な自分がいなければならない」山際による、長谷川評だ。
1947年、神奈川県愛甲郡愛川町に生まれた長谷川は、中学を卒業すると就職し、定時制高校に通いながら、山に登りはじめる。
「長谷川は、山に登りながら自分の意識が尖鋭化していくプロセスを、著書に書いている。
17歳のとき、会社の仲間とパーティーを組み、谷川岳へ登った。そして仲間が 一人、落ちた。
断末魔を思わせる叫び声が一ノ倉沢の谷に響き、恐怖に足がすくんでしまったという。その仲間は死んだ。長谷川は、山の厳しい現実を経験した。
『とことん勝負してやろう、山とは命のやりとりだ。いわば人生の勝負を壁に賭けてみようと思ったのは、この時がはじめてだといってよいだろう。山との勝負に勝つには、自分の技術を磨かなければならない。そう思うと、私は絶対にトップで登れる技術、精神力、体力を身につけなければならないと思った』
数か月後、今度は長谷川自身が転落する。30mほど、落下した。幸い、大きなケガにはならなかったが、精神的なショックは大きかった。パートナ ーは、無理するなという。トップをかわってやるからあとからついてこい。そういわれて、長谷川は立ちあがる。いや、おれがこのままトップを登ると。
恐怖から逃げてはいけない、克服しなければと、長谷川はきわめて直線的に克己心を説くのだ。
長谷川は、まず日本の山で初登攀の記録を作っていく。日本アルパインガイド協会の会員となり、いわゆるガイドとしての仕事も始めた。そういう実績があって初めてエベレスト登山隊のメンバーに加えられたわけだ。
しかし、エベレスト隊は彼にとってはうんざりするものだったらしい。そこでは例によって、誰がアタック隊として選抜されるか、トラブルにはならないまでも、人間関係のきしみが発生する。選ばれる人間と、残される男たち、である。
長谷川は何人かでパーティーを組んで山に登るとき、仮にトップを登っている人間が、自分より技術的に劣るとみると、即座に交代した。相手が撫然としようが怒ろう が、おれがトップをやるといって平然と登りはじめた。
パーティーは一本のザイル に結ばれている。一人の転落が他に大きく影響を及ぼす。下手な人間が先頭を切れば、みな危険にさらされてしまう―それが長谷川の論理だった。
みんなでかわるがわるにトップをやればいい、などという平等主義は、当然のことながら、山では危険だ。しかし、ワン・マンぶりを発揮しすぎれば人間関係はこわれてしまう。
長谷川がソロ・クライマーになっていくにはそういう背景がある。
一人で山に登りはじめると、長谷川はますます、ストイックになっていく。長谷川語録をピックアップしてみよう。この山男のダンディズムが見えてくる。
『アルピニストにとって、ハングリーさは必要である。だが、それは、アルピニストだけでなく、社会生活をしている多くの誰でもが持っているのではないだろうか。何かしたい、もっと価値ある生き方をしたい。充実した会話がしてみたいといった ように。みんなハングリーなんだと思う。私はたまたま山が好きで、山にその飢えを持っていった。そして、ひとつひとつ登っていくごとに私の飢えに対する栄養を山は与えてくれた。みんなの中に、きっと北壁があると私は信じている。その壁に向かって努力している人は、きっとまた新しい壁を見つけるだろう』
『負けてたまるか、というところから、もう一歩進んで、やるんだ、できる、と自分に言い聞かせ、たゆまぬ努力をすることにより、希望や理想も夢も現実に近づ いてくる。精神も肉体も極度に緊張し、ときによっては全身に腹の底から震えがくるような恐怖に打ち勝ち、怠惰をけちらしていくことによって勇気は弱い自分を素晴らしい経験へと引っぱっていってくれる』
長谷川は、これらの言葉を書斎に座って書き散らしたのではない。
指先に血がにじみ、その血が流れ出てこない。あまりにも気温が低いからだ。-30度をさらに下回っているだろう。強風が吹きつける。ピッケルを振るい、ザイルを結び、氷壁を一歩一歩よじのぼる、そういう体験のなかから出てきた言葉である。
アルピニストたちは、山へ向かう。自己を回復するために、だ。それをギリギリまで進めていくと、人はストイックにならざるをえない。遊び半分にやっていたの では、何も得られないからだ。ふだんからトレーニングを積み、節制せざるをえな い。
欲望をコントロールしなければ、目標に到達することなんてできない。おのずと、彼らはきまじめになってくる。自分自身に対して、まじめになってくるわけだ。
今こそ山の苦業は貴重である
今は欲望開放の時代だ。ボーッと口を開けて街を歩いていれば、何でも飛びこんでくる。物はいやという ほどあふれているし、オモシロそうなことは、自分で見つけようとしなくても、向こうから飛びこんでくる。
テレビではタモリが、毎日、笑っていいとも! といっている。芸能人は相変わらず、毎日のようにワイドショー向けの話題を作り出している。視聴者は、それを見て、バカねーといいながら笑っていればいいのだ。みんながみんな、快楽原則のなかで生きているかのごとくなのだ。
山の苦業は、今、貴重である。
ただ山の頂に達するというそれだけのために、おびただしいエネルギーを費やすアルピニストたちの行為は、現代人にアンチテーゼを投げかける。
長谷川は、ストイックに山に向かい、自分で自分をはげましながら苦しい登 攀をつづけてきた。その結果、何を得るか。例えば、次のようにいうのだ。
ほんの一センチの鋭い岩角に人間の四本の手足がかじりつき、零下二十度、風速 三十メートルの嵐に耐える。私はゆっくりとハンマーを元に戻すと、氷をしっかりと掴み、雪底の上にはいあ がった。その時、雲から放たれた太陽の閃光がキラキラとレモン色に輝いて、私の顔を叩いた。
私はこの陽光が忘れることはできない自然の祝福だと思えたのだった。そして両足でしっかりと頂上に立った』
グランド・ジョラスの、八日間にわたる登攀を終え、ついに頂上に立ったときのことを、彼はそう書いている。彼はその直後、トランシーバーを出して交信した。第一声は『爽やかだ』という言葉だった。
彼らのように極限を体験しに行く人間は少数派だ。社会のなかでは圧倒的に少数 派である。しかし、安全弁を自ら放棄してしまった彼らの生き方のなかに、キラリと光る真実が見え隠れしているのはなぜだろう。
どんな時代でも、実存状況を生きる人間は社会を撃つ。
長谷川は、グランド・ジョラス登攀中、張り残されたザイルをたびたび目にする。わざと残していったものではない。その地点まで登ってきて、何らかの原因で遭難してしまった男たちが残したザイルである。馬鹿バカしいほどひたむきで、愚かしいほど一所懸命な男たちの営為が、岩壁に残された一本のザイルから見えてくる。
『残されたザイルには人間の匂いがした』と、長谷川はいっている。
それは雪煙のかなたに消えていった男たちからの無言のメッセージである」
本書が発刊された1984年、ナンガパルバット中央側稜の単独登攀を果たした長谷川だが、1991年、彼もまた、ウルタルII峰で雪崩に巻き込まれ遭難死した(43歳没)
なお著者の山際も、1995年、胃がんによる肝不全のため46歳で急逝している。
第6章 孤高の人生をめざして
「何ごとかをなしとげようとするとき、人間は単独行動を選ぶことが多い。
しかし、なぜ、一人なのだろう。
人間は二人になると対立する。三人以上になると分裂する。困ったものだが、そういう癖がある。もっとも行動しやすい単位は一人である。
だから単独行を選ぶのだろうか。それだけでは説明しきれない。
アルプスの三大北壁を冬期に、しかも単独で登った世界最初のクライマー、長谷川恒男はこういっている。
『人間の一生は短い。その中で、たったひとつの生命が、自分自身の心の中で永久に生きていられる表現方法が、私の場合は登山だと思う。私は何故こんなことを考えるのだろうか。私は単独登はん者だからだ。ふたりのパーティーで登っている人たちにもきっと言えるかもしれない。しかし、何分の一しか感じられないかもしれない。それは、ふたりの場合は、ふたりでなしとげる総合的登はんの完了だからだ』
生きている証となる行為を何人かで一緒になってやれば、その喜びも何分の一かになってしまう。単独行の男たちには、基本的に欲張りなところがある。要するに彼らは、何もかも自分のものにしたいのだ。成功だけではない。失敗も自分の責に帰したい。
彼らは、個人主義者である。集団のために自分を犠牲にしようとは考えていない。自分のやり方を邪魔されたくはないのだ。
私の知り合いに、ボートのシングル・スカル競技の選手がいる。彼は高校時代までサッカーをやっていた。チームの中心メンバーの一人だった。しかし彼は最後までサッカーというスポーツになじめなかったという。
『ぼくがどれだけ一所懸命にいいプレーをしても、ほかの選手のミスで負けるときが、たまらなくいやだった。しようがないことだということはわかる。ぼくのミスで負けることもあるんだからね。でも、自分でやったことがちゃんと自分にはねかえってこないということは、つらい』
クライマーにも、二種類のタイプがいる。パーティーを組み、ザイルを結びあって一つの山に挑むことの素晴らしさを追求するタイプと、単独行を追求するタイプである。
単独行にこだわる人間には、自負心が脈打っている。何人もの人間が束になってやっと登った山をおれは一人で登りきってみせる、という思いである。単独行は、そのヒロイズムに支えられている。
しかし、いやなやつらだと思わないでほしい。彼らほど山に対する思い入れが深 い人間はいないのだ。ひたむきに山を愛してしまうからこそ、その山を自分一人のものにしたいと願うのだ。
きっと彼らは他のクライマーたちよりも、ヴォルテージが高いのだろう。いつも高熱を発している。その熱を冷ますには、ありきたりのことではたりない。十分にヒロイックな行為に身をゆだねなければならない。
ソロ・クライマーたちは、たしかに孤独である。他の仲間たちとうまく歩調を合わせることができない。社会にもどってきてもそうだろう。
これは長谷川が、徹底的に自身の内面と向き合った、ソロ・クライマーとしての特性ゆえかもしれない。
長谷川は、グランド・ジョラス登攀の模様を「北壁に舞う」という書に著しているが、これを山際は、「随所に、長谷川らしいきらめきが感じられる。彼は行動的でありながら、同時に内省的である」と評している。加藤の「雪煙をめざして」に対する評価とは、ずいぶん開きがある。
ニコラ・ジャジェールは1946、フランスに生まれたアルピニスト。医師でもあった彼の生涯は、高所における人間の生理的限界への科学的探求と、過酷な単独行への情熱が融合したものだった。
1980年、ネパールのローツェ(8,516m)単独縦走中に消息を絶つ。
彼の単独行の論理は、他者への依存を徹底的に排除する「厳格な自己完結性」であり、「自分の命の全責任を自分一人で負う」ことに至高の価値を見出していた。
ぼくらがニコラ・ジャジェールというアルピニストから学べることはたくさんある。
あえてむずかしい状況をつくることによって、面白さが深まるということも、忘れてはならないことなのだ。高い目標に挑戦することをこわがり、そこから逃げていると、人生ますますつまらなくなってしまう。低きに流れたら、人間、おしまいだ。高みに向かって自分を縛るからこそ、やりがいが出てくる。
ジャジェールは、「孤独」は寂しさではなく、研ぎ澄まされた意識状態に近いものととらえていた。単独行の伴侶となる「孤独」をどうとらえるか。
山際は「孤独が格好悪いものになってしまって久しい」と嘆く。
「最近、街を歩いていて気づいたことがある。一人で歩いている若者が少ないことだ。たいてい、誰かとつるんでいる。
そして、みなおしゃべりだ。情報交換というたぐいの会話。知ることによって安心し、知らせることによってホッとする。お互いに心の荷物をあずけあって、つながりあって生きている。
見えないロープで、お互いに互いを縛りあおうとしている。みな、本当は孤独なくせに、そのことを意識するのがいやだからつるんでいるように見える。本当の自分から逃げながら楽しさごっこをしているから、街は人形だらけだ。
ゲオルク・ウィンクラーのことを書いておこう。
ウィンクラーの名が知れわたるようになるのは、死後のことだ。彼は日記を残していた。その日記にはウィンクラーの十代の登山行がことこまかに書かれていた。それを見た大人のアルピニストは目を丸くしてしまった。経験を積んだクライマーにとってもむずかしいとされているアルプスの山々を、十代のウィンクラーは一人で登攀していたからだ。
ウィンクラーは単独登攀の孤独の中で恍惚を感じていた。彼はノートに「非常に愉快だ」と書き残している。
十九歳のとき、死が突然やってこなければ、彼はやがてすぐれたエッセイを書き残すようになったのではないだろうか。
芳野満彦というアルピニストがいる。
昭和六年生まれだから、もう五十歳をこえている。画家でもあり、同時に『山靴の音』という著書もある。
17歳のとき八ヶ岳の主峰赤岳を登山中に悪天候に遭い、やむなくビバーク。
翌日、行動を開始しようとするが、凍傷にやられた仲間は一歩も歩くことができない。そして二晩目のビバークがあけたとき、仲間は死んでいた。
かろうじて生き残った芳野も凍傷で両足指すべてを失ってしまう。
なぜ芳野のことをここで書いたかというと、彼は八ヶ岳の遭難から二年経った 昭和二十五年の冬、上高地徳沢園の小屋番をして一冬を過ごすのだ。約半年間、雪に閉ざされた山小屋に一人、こもりきりになる。
雪に閉ざされた上高地に半年間、身を置いてみようと思ったのは、友を失った遭難事件と無関係ではない。孤独の世界に入りこもうとしたわけだった。
『ただ一人じっと雪の山々を眺め、山に逝った友を偲び、その冥福を祈るように静かに静かに前穂高の頂に陽が沈むや、一瞬にして暗黒の世と化す大自然、感傷も静寂も暗黒の渦に巻きこまれ、孤独と静寂とが風雪となって私に襲いかかってくるのだった』
毎日毎日、闇とたたかいながら、ある日、彼はモルゲンロート(夜明け)を迎える。長い間、雪を降らせる雲が重くたれこめていたのだが、その朝は違った。芳野は思わず外に飛び出していく。
『いったいこの景色を何人の人たちが知っていることだろう。おそらくこの姿に接した人は数えるほどしかいないと思う。私は自然と涙がわき出てきた。山にいる喜びと旭光が、私の魂の底に貫いていたのだろう』
そのイメージは彼の心の深いところで一生輝きつづけるわけである。
ヘルマン・ブールは1924年、オーストリア・チロル州インスブルック出身の登山家。
1953年、「魔の山」と呼ばれたナンガパルバットの初登頂を無酸素で成し遂げた。
このときの登攀では、パートナーが体調不良になったため単独で登頂するが、下山時に8000mの高度で立ったままビバークを強いられる。
魔の山が夜をむかえ、あたりが漆黒の闇に包まれると、ブールは幻覚におそわれる。
『おい、ぼくの手袋をみなかったか?』
こうはっきりいうのをぼくは聞いた。ぼくはうしろをふりかえる。だが、だれそれは”死”への誘惑だ。やっと誰かがきてくれた、やっと家にたどりついた……そういう幻覚におそわれ、動き出す。その直後、虚空に身を躍らせている。そういうふうにして山に散った生命をいったい、いくつ数えることができるだろう。その瞬間の記録は残っていない。 死者は何も語らないのだから。しかし、決して少ない数ではない」
ブールは、出発から41時間かけてキャンプに生還する。戻ったとき、ブールの顔は高所衰退と過労からまるで老人のようになっていたという。さらに凍傷により足指2本の切断を余儀なくされた。
「それでもブールは、他のアルピニストがみなそうであるように、死の寸前から帰還人間というのは、ホントに困ったもんだと思う。
街に出ても、刺激が足りない。単に騒がしいだけだ。血がちっとも騒がないのだ。
巨大な氷片が数千メートルの虚空を落下し、氷河に落ちる。こなごなになった氷 片は雪煙となって舞いあがり、やがてそれが幅数キロの雪崩となって氷河を下って いく。その一瞬の轟音、光・・・・。アルピニストたちはそのとき、自分の心につきあげてくるものを感じるのだ。
ブールが狙ったのは、ヒマラヤの西、カラコルム山脈のブロード・ピークである。
そのまま、彼らはもう一つの計画を実行に移した。近くの山、チョゴリザも登頂 してしまおうというのだった。チョゴリザは、当時はまだ未踏の山だった。処女峰である。
ヘルマン・ブールは7200mの稜線から約1000mにわたって北壁の下部に落下したと思われる。
「『山は、ロマンチストじゃなければ登れません』
そのつぶやきを、ぼくは直接自分の耳で聞くことはできなかった。彼もまた、山で命を落とした一人だからである。
彼の名は松濤明という。1922年宮城県仙台市に生まれた彼は、中学時代に教師に連れられて登った燕岳・槍ヶ岳をきっかけに、登山に目覚める。
『山のかなたの目に見えぬもの』にひかれ、彼は黙々と山に入っていく。
尾根を辿り、沢を下り、春の風雪に巻きこまれながら山を歩きつづける。その間、ポツリポツリと人間に出会うだけである。
人がいなくなり朽ち果てた部落に足を踏み入れ、漆黒の闇のなかで一人、火を燃やしビバークする。
それほどの孤独を、彼はなぜ求めるのか。
『空は今日もまた素晴らしく澄み渡って、岳は美しく輝いている。快い微風が頬をかすめ、暖かい春の一日である。あの白く輝く岳の奥から、ひなびた不可思議な旋風が風に乗って伝ってくる。それが無性に私を引きつける。これを見、あれを聞く時、山へ行くのが苦しいから山へ行くのでなく、また楽しいから行くのでもない。純粋に、一つのものを作りあげること、のみを目指して山へ入れるような、氷のような山男になることのいかに困難であるかをしみじみと感ずるのだ』
一つのものを作りあげること、そのことに彼は固執している。山と対峙する自分を完成させようとしているかのようだ。彼は求道者のようにも見える。
孤独のなかで自分を見つめる。長い歩みのなかで自分を見つめつづける。そうすることによってしか得られない何かを、彼は求めていたのだ。そのために松濤は、孤独と格闘することをいとわなかった。
単独行の人たちは、誰を見てもきわめてストイックである。ストイックに自分を律していかないと、望む結果が得られないからである。同時に、彼らは思いの深さを持っている。彼がつきとめようとしているものの根は深い。深いから、くりかえ しくりかえし、長く苦しい旅をする。
松濤は、最後まで戦うのも命、友の辺に捨てるのもまた命、と書き残し、その場を動かなかった。
ぼくらはその決然たる意志に向かって、いうべき言葉を持てない。
この稀代のアルピニストは、凍りついた手にペンを持ちながら、短い言葉を残し、 それによって彼の激しい意志を、後の時代に伝えたのである。孤独を愛し、孤独と闘い、そのかなたに何ごとかを作りあげようとした人間の苛烈な意志は、筆舌に尽くしがたいほど、われわれの心を揺さぶるのだ。
松濤が、最後に書き残したメモは、凄絶ですらある。
『一月六日 フーセツ 全身硬ッテカナシ ナントカ湯俣マデト思ウモ 有元ヲ捨ルニシノビズ 死ヲ決ス。 オカアサン アナタノヤサシサニ タダ、カンシャ。一足サキニ オトウサンノ所へ行キマス。ナンノコウコウモ出来ズ、死ヌツミヲ、オユルシ下サイ (空白) 有元ト死ヲ決シタノガ六ジ 今、十四ジ ナカナカ死ネナイ ヨウヤク腰マデ硬直がキタ 有元モソロソロクルシ、ヒグレトトモニスベテオワラン』
死を覚悟して遺言を認めた後、1月6日に死去、享年26であった」
遭難中に記した日記は死後、『風雪のビバーク』というタイトルで出版され、「最後の手帳」は、大町山岳博物館に収蔵されている。
山際は言う。
「ぼくはここで、のっぺりとした現在に対するささやかな抵抗をこころみてみようと考えている。雪煙のなかに消えていった男たちをいま一度、よみがえらせることによって、彼らの切羽つまったロマンティシズムを解剖してみようと思うのだ。残されたわれわれが、鮮烈に生きることを、つかの間、思い出すために、である」